| 農薬通信 |
2003年9月号『果樹』
|
|
登録日2003/09/09
|
| ||||||| モモハモグリガの秋防除 ||||||| モモハモグリガはモモの主要害虫で、幼虫が葉肉内を食害しながら進み、その被害の跡が白く線を描いたように見えることから「エカキムシ」とも呼ばれています。 本年山梨県内では多くの園で発生が見られ、多発した園では落葉も見られました。 現在は収穫後ということで防除も手薄になり、来年への越冬密度が高くなってしまう可能性があります。 今後の発生に注意しながらモモハモグリガの秋防除をしっかりと行いましょう。
< これからの防除 > 山梨県果樹病害虫防除暦にも記載されているとおり、スプラサイド水和剤1,500倍を用いて防除してください。 本防除により来年への越冬密度を下げると同時に、近年問題となっているウメシロカイガラムシの防除(3回目の幼虫発生期)にもなります。 10日から2週間間隔での複数回の散布が効果が高いと思われます。 今年の被害は早生品種を中心に収穫後の防除に手が回らなかった園に多く見られました。 ※実際の使用にあたっては登録内容を守り、注意事項を確認の上ご使用ください。 また、初めてご使用になる際は最寄の普及センター、JA等の指導機関にご相談ください。 |
 |
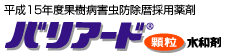 |





