| 農薬通信 |
2001年12月号『一般』
|
|
登録日2001/12/18
|
| ||||||新害虫「トマトハモグリバエ」|||||| 平成13年11月13日付で山梨県より新害虫「トマトハモグリバエ」の病害虫発生予察特殊報が出されました。 本種は平成6年に本県で発生が確認されたマメハモグリバエと同様に作物の葉肉内を食害・潜行し、葉に白く絵を描いたような被害を出します。 本県で新しい病害虫の発生が確認されたのはトマトサビダニ以来2年5ヶ月ぶりとなります。 トマトハモグリバエは海外からの侵入害虫で、アメリカ大陸を中心に現在はアフリカやアジアにも分布しています。 国内では平成11年に沖縄、山口、京都で初めての発生が確認され、その後発生地域を拡大し、関東・東海地域では神奈川県に続いて本県が二例目の発生確認となります(全国18府県で確認)。 < 被 害 > トマトハモグリバエは、これまでのマメハモグリバエではあまり問題とならなかったウリ科作物で特異的に多発生する傾向があります。 幼虫が葉肉内を食害潜行し、絵描き状の被害を発生させます。 キュウリ、トマトでは上位 葉まで幼虫の潜行が認められ、寄生が著しい場合には葉が白化します。 < 寄主植物 > 本種はマメハモグリバエと同様に、ウリ科、ナス科、マメ科、アブラナ科、キク科など極めて多くの植物に寄生する多食性種です。 国内で寄生が確認された植物は以下のとおりです。
< 形 態 > 形態は成虫、幼虫ともマメハモグリバエやナスハモグリバエとほぼ同じで、肉眼では識別 できません。 成虫は体長が1.3〜2.3mm、翅長約1.3〜1.7mmの頭部の大部分が黄色をした小型のハエで、外頭頂剛毛の着生部が黒色、脚は黄色です。マメハモグリバエやナスハモグリバエの頭部外頭頂剛毛及び内頭頂剛毛の着生部が黄色であることが本種との識別 点となり、種の識別には実態顕微鏡下での観察が必要です。 卵は直径0.2〜0.3mmの楕円形で半透明のゼリー状をしています。 幼虫は淡黄色のウジ虫状で3令幼虫の体長は約3.0mmです。 蛹は黄褐色の俵型で体長が約1.3〜2.3mmです。 < 生 態 > 卵は雌成虫が産卵管で葉に開けた穴の内側に産み付けられ、孵化した幼虫が葉肉内をトンネル状に食害します。老熟幼虫は葉から外に出て地表に落下し、土中で蛹になります。 葉への被害(絵描き症状)や蛹化の方法はマメハモグリバエと酷似し、識別 は困難です。 卵から成虫になるまでの期間は、気温20℃で約27日、25℃で約18日、30℃で約14日です。 < 防 除 > 現在トマトハモグリバエに登録のある薬剤がないためマメハモグリバエに有効で、作物登録のある薬剤で同時防除を行ってください。 トリガード液剤、アファーム乳剤が本種に効果 が高いことがこれまでの国内の試験より分かっています。 表1 トマトハモグリバエに効果の確認されている剤及び作物登録
耕種的防除として以下の点に注意してください
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
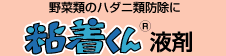 |
|
